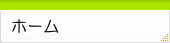
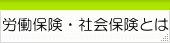
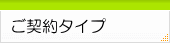
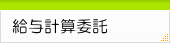
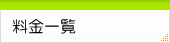
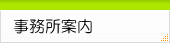
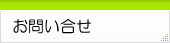
|
|
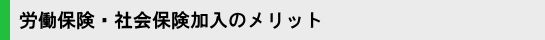
労働保険・社会保険加入の最大のメリットは、良い人材の確保でしょう。会社が成長するには人を雇い入れる必要があります。当然労働者としては社会保険にしっかりと入れる福利厚生の良い会社を選びますので、社会保険に加入していない会社に来る可能性は非常に低いと思われます。
以下では労働保険・社会保険それぞれの保険のメリットを分かりやすく説明させて頂きます。
|
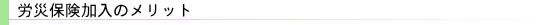
労災保険(労働者災害補償保険)は従業員の方が業務中にケガなどで負傷してしまった(業務災害)時に、本来は使用者責任で会社が、その治療費と休業してしまった場合にはその間の賃金を支払わなければならないのですが、その掛かってしまった費用が国の労災保険から給付が行われます。
さらに通勤途中の事故(通勤災害)についても労災保険から給付が行われます。
|
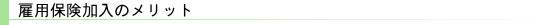
雇用保険は労働者が失業してしまった場合に失業給付を受けるだけと思われていますが、実際には他にも色々なメリットがあります。
まず妊娠、出産や高齢なで労働能力が低下してしまった時に給付を受けられます。(具体的には高年齢雇用継続給付や育児介護休業給付など)
会社としての最大のメリットは助成金の受給です。費用の説明のページで、雇用保険料が本人負担額より会社負担額が多いのは、その差額が助成金などに充てられているためです。なので助成金を受給するときは必ず、毎年の労働保険料を正しく納付しているか確認の資料の提出を求められます。
|
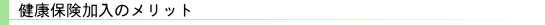
健康保険は市町村が行っている国民健康保険よりも多くの給付があるということです。
特に大きな違いは傷病手当金の支給でしょう。会社を4日以上連続で休むような病気になってしまった場合に、1日当たり標準報酬日額(1ヶ月当たりの賃金を社会保険の月額に当てはめて30で割って1日当たりの金額に直したもの)の3分の2の額が支給されます。
これは従業員だけでなく代表者や役員の方も対象になりますので非常に手厚い給付になります。
その他にも出産手当金の支給があります。産前産後休業中に1日当たり標準報酬日額の3分の2の額が支給されます。
健康保険の大きなメリットとしては、ご家族が被扶養者として加入できるので保険料が発生しません。 |
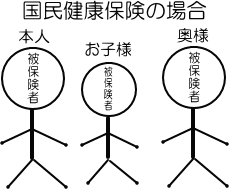 |
このように国民健康保険の場合はご家族の1人1人が被保険者として加入することになりますので保険料は3人分掛かってしまい、毎月高額な保険料を支払うことになってしまいます。 |
|
|
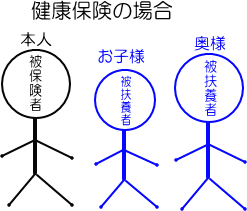 |
健康保険の場合は被保険者は本人1人のみになり、保険料も1人分のみです。ご家族のお子様と奥様は被扶養者となりますので保険料は掛かりません。
※被扶養者には所得要件があり、被扶養者の年間収入は130万円未満でなければなりません。 |
| 上記の図のように、健康保険に加入することによって保険料が発生しません。 |
また会社として毎月保険料を支払わなければなりませんが、その保険料に関しても健康保険組合に加入することができれば変わることがあります。
通常健康保険に加入する場合は協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入することになりますが、業種にごとに健康保険組合(飲食業や製造業)があり、そういったところに加入することによって保険料が変わります。
健康保険組合は組合ごとに保険料率が違うので、出来るだけ保険料率の低いところに加入するこが重要です。
|
| 月給30万円 |
保険料率 |
保険料 |
| 協会けんぽ |
99.7./1000 |
29,910円 |
| 健康保険組合 |
70/1000 |
21,000円 |
| 差額 |
29.7/1000 |
8,910円 |
注:協会けんぽの保険料率は2,009年9月から都道府県ごとに変わります。(81.5/1000〜82.6/1000)
上記は東京都(81.8/1000)の場合です。 |
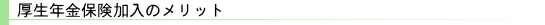
| 20歳以上の人は全員国民年金に加入しますが、法人や5人以上の個人事業所(1部業種除く)で働く人は厚生年金に加入することになります。厚生年金は2階建て年金ともよばれ、1階部分が国民年金で2階部分が厚生年金になりますので、厚生年金に加入することにより将来国民年金と厚生年金の両方の年金の給付を受けることができます。 |
また万一事故などで障害を負ってしまったりした場合でも、生涯にわたり障害厚生年金を受給することが出来ます。また死亡してしまった場合遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。
もし仮に国民年金しか加入していない場合は、障害基礎年金又は、遺族基礎年金と極めて少ない給付しか受けることが出来ません。 |
保険料に関しては国民年金よりは高くなりますが将来の手厚い給付を考えれば、絶対に加入すべきです。
下の図で分かりやすく説明させて頂きます。 |
| 国民年金のみ加入している場合 |
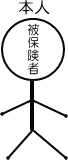 |
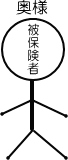 |
| 加入している年金 |
国民年金 |
国民年金 |
| 毎月支払う保険料 |
国民年金 |
国民年金 |
65歳から受けられる
年金給付 |
国民年金 |
国民年金 |
| 厚生年金に加入している場合 |
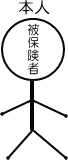 |
 |
| 加入している年金 |
厚生年金 |
国民年金 |
| 毎月支払う保険料 |
厚生年金 |
なし(第3号被保険者) |
65歳から受けられる
年金給付 |
厚生年金
国民年金 |
国民年金 |
※国民年金第3号被保険者:一般的にはサラリーマンの妻(20歳以上60歳未満)を指す場合が多いです。
上記の図を見ていただいてお分かりと思いますが、サラリーマンの妻は国民年金に加入しているので保険料を払わなければならないのですが、国民年金第3号被保険者という少し特殊な被保険者になるため、国民年金に加入しているにも関わらず保険料の支払いが不要なのです。
さらに本人も厚生年金の保険料を支払うだけで将来国民年金も受給出来ること。
このように厚生年金に加入することにより、多くの面で優遇されたり、手厚い給付を受けることが出来ます。
|
|

